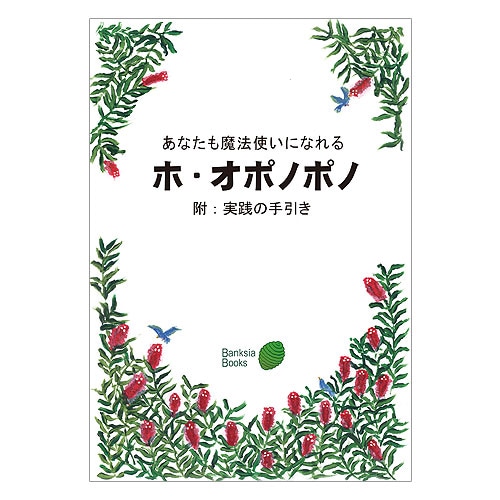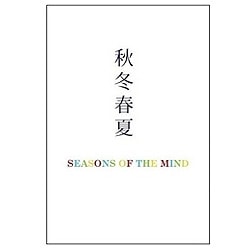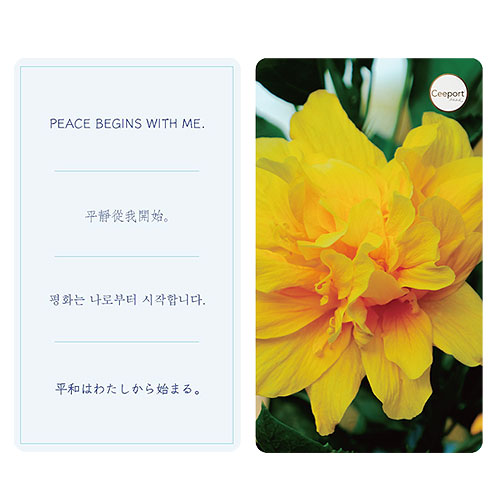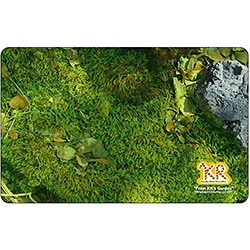クリスティーンさんへのインタビュー(3)
今回は、長年講師としてご活躍のクリスティーン・レイマカマエ・チュウさんにお話を伺います。
視点を180度変える
―― 「許せない」というテーマにハッとしました。「どんな出来事も人も許すべき」というのが一般的だと思うので、「許したくない!」「許さなくちゃいけない」と苦しんでいる人たちがどんな風にクリーニングに取り組めばいいのかというヒントになりそうです。
クリスティーン・レイマカマエ・チュウさん(以下、クリスティーンさん) 「許す」というのは相手があって成立する概念ですよね。でも「外なんてない!」のだから、まずは一切の「外側」を断ち切るんです。つまり誰かを自分以上に丁重に扱ったり、自己犠牲を強いたり、他の人の世話を焼くことに一生懸命になっている状態をいったん止めること。そして視点を180度変えて、自分自身の内側を見て、「どんな思いが私をここまで怒らせているの?どうして気分を害しているの?」「この感情を手放すことができる?」と自分自身に聞いてみるんです。
―― 「許さなくちゃいけない」「手放さなくちゃいけない」と自分をがんじがらめにすることで、溜まった感情を握りしめて不満を抱えて怒っているのは、確かに相手があってのことですよね。まずは相手との見えない糸を断ち切って視点をひっくり返すのは、なかなか難しいのではないでしょうか。
クリスティーンさん それは本当の意味で、自分自身のケアに集中するということ。そうすると逆説的だけれども、人間関係は相互に関わって反応し合っているものだから、私たちが本当には何を欲していたのか、鏡のように家族やまわりの人たちが見て気づく機会にもなる。自分を最優先することが大事なんです。特に妻とか母親という役割に注力して自分を後回しにしてきた女性たちにとって、この「自分を最優先にする」という選択は難しいことかもしれませんね。
―― 自分の人生を生きるという選択すらできないと思い込んで諦めている側面もありそうです。
クリスティーンさん そうなのです。特に子どもたちは大人たちのすること一挙手一投足を見逃さず、私たちが自分をないがしろにしているのか、自分をきちんとケアしているのか、私たちの態度から人生を学んでいます。だからこそ一日中家族の面倒に追われて疲れ果てた末にようやく一息つくという生活ではなくて、ストレスを感じたら「ちょっとタイム!」と自分を労わる時間を作ったり、物理的に距離を置いたりして、HAの呼吸をして自分自身を落ち着かせるようにする。そうすると実は、家族みんなが落ち着くということが分かってくる。自分自身がストレスまみれ不安まみれだったら、他のみんなもストレスまみれだということ。これは家庭でも職場でも同じことなんです。
自分をリスペクトすること
―― 誰もが「自分を犠牲にして誰かの面倒を見続けなくてはいけない」という監獄の中の囚人なのかもしれませんね。理想の何者かになろうとして消耗している。
私は2年前に離婚したとき、息子が夫と同居することになったので自分が思っていた以上に辛くて日々がクリーニングに溢れていました。気づきの連続だったのですが、最近息子から「僕も最初は辛かったけど、離れて暮らすようになってよかった。だってママは過保護で過干渉だったから、自分の人生を自分の責任で決める自信もなかったんだ。今は家事だってできるし、自立できるようになったでしょ。あのままだったら僕マジでヤバかったよ」と言われて救われたような「それは確かにそうだった…ゴメンね」と笑ってしまいました。元夫とも冗談交じりに話せるようになりましたし、今になって離婚がパーフェクトだったのかなと気づくことが多々あります。
クリスティーンさん それは驚くほど大きな跳躍だったでしょうね。先祖代々同じような生活を繰り返すなかで、人生に別の選択肢があるだなんて考えもしないわけだから。息子さんにもご自身に対してもすごいギフトになったでしょうね。
私も最近離婚して、子どもたちが週代わりに行ったり来たりしています。いないときには寂しい気持ちもあるのだけれど、毎日24時間ひっきりなしに動いて心配して疲れ果てるのではなく、リフレッシュして若返る時間もある。子どもたちが戻ってきたときに新しい自分で接することもできる。物理的に一緒にいない時でも、いつでも子どもたちは親を見ていることにも気づきました。母親が自分自身を敬ってケアするという姿を見せることが鏡になって、子どもたちも自分をリスペクトして自立できる。それこそが本当の愛かもしれませんよね。
自身の内側こそがリアル
―― 自分を敬うというところで、もう一度「許せない」というテーマに戻って「視点を180度変える」ことについて、もう少し伺いたいです。
クリスティーンさん 「外側というのはリアルではない」ということ。今、自分自身が何をどんな風に感じているのかこそが、リアルなんです。たとえば怒りや後悔を抱えているときこそ、怒りのきっかけとなった出来事や人との繋がりを断って、自分自身に集中して、「どんな思いを抱えているの?それはどうして?」と自分自身に問いながら、その感情を容認する。それは相手のことはどうでもいいという意味ではなくて、許すことに対してわざわざ取り組む必要はないということ。平和を思い描いてそのゴールを目指すのでもなく、平静さを装って瞑想するでもなく、「何が原因かわからないけれど、この現象や相手と自分の間にあるしがらみを断ち切って正したい」と決めるかどうか。今この瞬間に握りしめている思いを手放すかどうか。
それでも毎日のことだから、これはギフトだったんだと感じられる瞬間もあれば、翌日にはさらなるゴミが現れて「あ―!!」ってなることもある。ちっとも有難く思えない時もあるし、外側に囚われることもある。だけど、どんな自分でも向き合って「できるだけ手放せるようにしている」というのが正直なところですよね。愛とかセルフケアとか、巷で言い尽くされてチープになっているけれど、その時にできる小さな小さな一歩を続けることですよね。
―― クリーニングが終わりなきプロセスに感じて、気が遠くなって投げ出したくなることもあります。講師の方々はどんな風に取り組み続けていらっしゃるんでしょうか。
クリスティーンさん 講師だから無口で平和で穏やかな人だと誤解されることも多いですけど、とんでもない!一日中狂ったようにバタバタイライラするんですよ(笑)。人間って感情があるのが普通なのだから、怒ってもわめいてもイラついてもいい。ドアを駆け抜けるように忙しくしているときも、運転しているときも、怒り狂っているときも、いかなる感情が渦巻いているときでも、自分が適用できるツールを使って内側で取り組めるのがSITHホ・オポノポノのいいところだと思っています。
そして「目を見開いて目の前の現実を直視する!それこそが今取り組む材料なのだから」というところも気に入っています。現実生活と密接に関わっていて、インタラクティブでいつだって人生のプロセスだから、ありのままを受け入れながらできることでクリーニングを続けて人生を進んでいく。モーナ女史もいつも穏やかで落ち着いた人だったわけじゃなくて、怒るときもものすごく突飛なときもありましたよ。だけどツールを用いてインスピレーションが得られたら実行に移す。インスピレーションを伝える。「こうしなくてはいけない」ではなくて、あなた自身であることが一番重要なんですよ。
―― 苦しみの奥の奥にある自分の思い方や考え方、信念に気づいて自分を大切にしてあげる。そうすることで手放して、クリーニングで嘆願して委ねる。「許せない」という苦しさがあるからこそ、自分を深く知るヒントになって「わたし」として生きる力をくれるのかもしれませんね。やはりすごいテーマです。
次回に続く
(文責:高木 みのり)
(『元気な暮らし』2022年8月号掲載)
クリスティーン・レイマカマエ・チュウ

1998年に初めてSITH®クラスに参加して以来クリーニングを実践し、現在はアメリカとカナダで講師を務めている。3人の子育て、建設会計で2つの仕事、クリーニングを通して人生そのものを実用的な側面にも応用している。
当記事に関して
※当記事は(株)トータルヘルスデザイン発行の無料月刊情報誌『元気な暮らし』に掲載された記事を元に再構成をしております。
『元気な暮らし』では毎月最新のインタビュー記事を掲載しております!
| ご購読はこちらから ↓ | グッズのご注文はこちらから ↓ |
 |
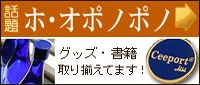 |